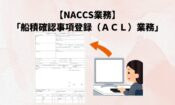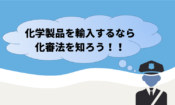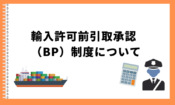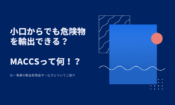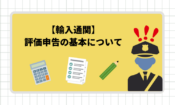【輸入通関】知らない間に申告漏れしているかも!?評価申告の基本を知っておこう!
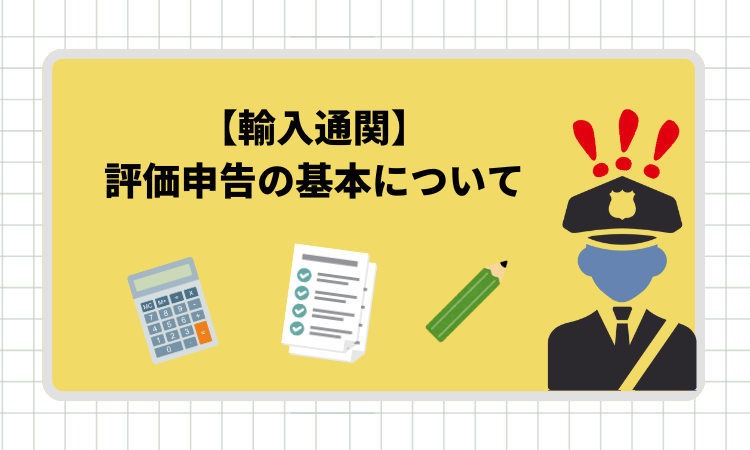
貨物を日本に輸入する際には、原則として貨物の輸入取引価格をもとに「課税価格」を決定し、税関に輸入申告を行います。この課税価格から算出される関税・消費税を納税することで初めて輸入許可を受けることができます。課税価格は、一般的には以下の3つの要素で構成されます。
- インボイス価格
- Arrival Noticeに記載されている諸チャージ(日本の港に到着後に生じる費用は除く 例:日本側のTHCなど)
- 当該輸入貨物にかかる外航貨物海上保険の保険料(付保していない場合は加算不要)
ただし、上記以外にも課税価格に含めるべき費用が存在するケースもあり、このような場合に課税価格を補正するために行うのが評価申告となります。この記事では、輸入事業者が押さえておきたい評価申告の基本についてご紹介いたします。
輸入における課税価格について
関税定率法第4条において、課税価格は現実支払い価格+加算要素である旨が規定されています。現実支払い価格とは、買い手から売り手に対して現実的に支払う価格(=インボイス価格)をいいます。そして加算要素は、現実支払い価格に含まれていない以下の費用を指します。
①輸入港までの運賃、保険料その他の運送関連費用
➁輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される仲介料 その他の手数料(買付手数料は除く)又は容器・包装の費用
③買手により無償で又は値引きして直接又は間接に提供された 物品又は役務の費用のうち以下のもの
- 輸入貨物に組み込まれている材料、部分品等
- 輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型等
- 輸入貨物の生産の過程で消費された物品
- 技術、設計その他の輸入貨物の生産に関する役務
④輸入貨物に係る特許権等の使用に伴う対価で、輸入取引の条件として買手により直接又は間接に支 払われるもの
⑤買い手による輸入貨物の処分等による収益で売手に帰属するもの
(zeikan201706016_1b.pdfより引用)
①~⑤まで、課税価格の構成要素について沢山でてきましたが、「課税価格」とは「現地から日本に商品が到着するまでにかかったトータル費用」というのが基本的な考え方となります。この認識で加算要素を見てみると、いずれの費用も支払わなければ商品自体製造できなくなるものや、輸送できなくなるものであることが分かります。
評価申告による補正が必要な場合について
一般的には、冒頭に挙げた3つの要素(インボイス価格・現地から日本までにかかった諸費用・海上保険料)を合計することで課税価格を算出することができます。しかし、もし加算要素が別途発生しており、その金額がインボイスに記載されていない場合は、評価申告によりその費用を別途加算する必要があります。実際に当社での通関実績においても、以下のような評価申告事例がありました。
- 輸入者と輸出者を仲介させる仲介業者へ支払う仲介手数料(加算要素②のケース)
- 商品を製造するために輸入者から輸出者へ無償提供した材料代や金型代(加算要素③のケース)
なお、材料代や金型代については、当該材料等を日本から現地に送る際に生じた海上運賃や海上保険料も評価の加算対象となるためご注意ください
申告価格から控除できる費用について
ここまでは加算要素について紹介しましましたが、逆に課税価格から控除できる費用もあります。控除できる費用については、関税定率法施行令第1条の4において以下の通り規定されています。
- 輸入申告時以降に行われる据え付け、組立て、整備又は技術指導に要する役務の費用
- 輸入港到着後の運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用
- 本邦において輸入貨物に課される関税その他の公課
- 延払い金利
上記については加算要素とは違い、日本の港に到着した後にかかる費用や輸入取引後に発生する費用である点が特徴となります。これらの金額について明らかになっている場合は、課税価格から控除することができます。ただし、控除できる金額が明らかでない場合は、その金額も含めて申告することになります。例えば、建値DDPで輸入取引を行う場合、インボイス価格には日本到着後の国内運送費等が含まれますが、この国内運送費を明らかにできる場合に限り、課税価格から国内運送費を控除して申告することができます。
評価申告で必要な書類について
評価申告を行う必要がある輸入取引の場合は、以下の書類を準備した上で課税価格に加算します。
- 評価申告書
- 加算金額が分かる書類
評価申告書については、関税がFREEの場合や、課税価格の総額が100万円以下の場合は提出を省略できます。ただし、あくまでも「評価申告書の提出」を省略できるだけで、課税価格への加算は必要ですので、ご留意ください。
また、後ほど述べる包括評価申告のように、継続した輸入取引がある場合は、評価申告書の提出が必要となります。
個別評価申告と包括評価申告について
評価申告には、輸入申告の都度、評価申告書を提出して行う「個別評価申告」と、個々の輸入申告に先立って事前に包括的に評価の申請を行う「包括評価申告」の2種類があります。
一定期間内に同じ内容の輸入取引を反復して継続的に行う場合においては、包括評価申告を行うことにより、適用期間内は個々の輸入申告における評価申告書の提出を省略できるメリットがあります。
評価申告書の様式については個別評価申告・包括評価申告共に、一般的には以下のURLにおける評価申告書Ⅰの様式を使用します。
https://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_C/C5300.pdf
包括評価申告における評価金額の加算方法について
包括評価申告において、加算要素となる金額が一括して現地に支払われている場合などは、適用期間内に輸入される個々の数量等に応じて加算金額を按分する方法と、初回輸入申告時にまとめて一括加算する方法のいずれかで申告することができます。
ただし、税率が異なる複数品目に評価金額がまたがる場合などは、一括加算する方法は取れず、個別評価申告を行う必要があります。
おわりに
今回は、最低限おさえておきたい評価申告の基本に絞ってご紹介しました。評価申告の加算漏れは税関の事後調査によって発覚するケースが多いです。当社のような通関業者においては、いただいている通関書類以外の部分は見えないため、評価加算すべき費用の有無を判断することはできません。そのため、まずは輸入者様がこの記事でご紹介した加算要素があるかどうかを見直していただき、必要に応じて通関業者や税関にご相談されることをお勧めいたします。
もし事後調査の結果、納税額が不足していた場合は、不足税額に加えて過少申告加算税や延滞税が発生する場合もあるため、自主的にチェックし、ミスに気が付いたら早めに修正申告を行うことが重要です。
輸出入についてなにかご不明点がございましたら、当社までお気軽にお問い合わせください。